
『平宗』で夏のご馳走、柿の葉寿司にチャレンジ【手作り体験】
関西在住のアラフォー編集者・おばやしが体験型施設に潜入し、 全力レポする連載「タンケン!タイケン教室」。 第9回目は『平宗』へ。柿の葉寿司を通して、奈良の食文化にも触れる体験となりました。
contents
実は夏のご馳走・柿の葉寿司
鹿が草を食み、亀が優雅に泳ぐ猿沢池から少し歩くと風情あるエリア。『平宗 奈良店』は猿沢池から南へ数分の場所にある。 レストランも併設された観光客にも人気の店舗。2階の体験会場へ。
「まずはこちらを」と柿の葉寿司の歴史を紹介するDVDを見せていただく。柿の葉寿司を手作りするお母さんたち、柿畑でサイズを計りながら収穫する柿の葉、代々継がれる米づくり…丁寧な仕事ぶりと美しい映像に見惚れる。手の込んだ映像はなんと、奈良出身の映画監督・河瀨直美さん作だそう…のっけからなんとも贅沢。
「山深い奈良・吉野では、海の魚は滅多に口に入らないご馳走でした。熊野から届く塩漬けの鯖と酢飯を合わせ、柿の葉で包んだ柿の葉寿司には、海の恵み、山の恵み、地の恵みが詰まっています。江戸時代から夏祭りのご馳走として各家庭で作られていた郷土食であり保存食なんですよ」と、店長の黒木さん。
柿の葉寿司といえば最近では駅やデパ地下でも売っているし、季節なんて考えたことがなかったが、旬があったんですねぇ。
包んで押して、職人技をタイケン
柿の葉寿司のお勉強したら、早速実践。
黒木さんが一工程ずつゆっくりと見せてくれるお手本を頼りに進めていく。
吉野杉の板には、成形されたものとそうでないものの2種の酢飯が置いてある。
成形されたものをお手本に4等分し、両手でこすり合わせるように伸ばして俵型に。
次に、柿の葉の中央に鯖→酢飯の順に置き、手前から葉で包む。 2回転がして筒状にしたら、鯖が上に来ていることを確認して左右を折る…と。
「ご飯を挟み込むようにして、右手の人差し指と親指で葉っぱの中央を真上からキュッと押さえます。ラッピングのキャラメル包みの要領ですね。あまりきれいにしなくても大丈夫です。ちょっと見ててくださいね」。
……って、早っ!
体感一瞬、時間にして3秒弱。まさに瞬き厳禁の職人技ッ。
昔は一個ずつこうやって作ってたんやなぁ~と呟くと、
「今でもほぼ手巻きなんですよ」。
え?『平宗』の企業規模で、手巻きだと…?
「専用の押し型は使いますが、柿農家さんが丁寧に育ててくれた葉には個体差もありますしね」
なんという職人魂…。
そうこうしているうちに完成した8つの柿の葉寿司を箱に詰めていく。箱は2本の棒が溝にはまる構造になっていて、上から押して棒をゴムで固定すると、重石になっていよいよ「押し寿司」になるという寸法。
「今日作っていただいたお寿司は明日が一番おいしいです」。
なんかじぃ~んとくるお言葉。
明日はきっとい~い日になる♪である。
完成後、箱を持つとずっしり重い。
「柿の寿司1個に対してだいたいにぎり寿司2貫分ぐらいのご飯が入っているんです」。ああーそっか、「押す」からね?
(心の声)これ、登山の行動食
にもってこいじゃない? 葉が天然の防腐剤だし、箸もいらないしお腹は膨れるし。昔の人はホントに偉いよね…。
お買い物必至⁉の体験予約方法
約45分の体験は奈良店のほか吉野本店や天理の「便利館」など各店で実施されていて、観光の途中でも気軽に参加できる。
※定員、スケジュール等は開催場所によって異なります。詳細はHPをご確認ください。
【平宗 奈良店の場合】
料金:
鯖・鮭8個入製造の場合:1名2000円(9月から2200円)
鯖・鮭12個入製造の場合:1名 2600円(9月から2750円)
定員:2~50名程度(要予約)
体験スケジュール:繁忙期を除く平日 15:00~、16:00~の2回
予約はこちら
data
- 店名
- 平宗 奈良店
- 住所
- 奈良県奈良市今御門町30-1
- 電話番号
- 0742-22-0866

writer

おばやし零余子
obayashi
兵庫県宝塚市在住の独身アラフォー編集者。酒と酒場好きで、年々大きくなる身体に危機感を覚え山登りに目覚めるが、一向に痩せる気配なし。最後の晩餐は雑煮。
recommend


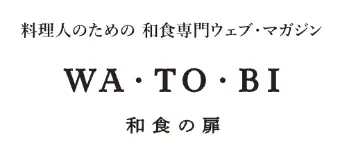
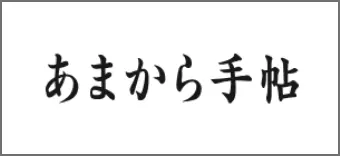
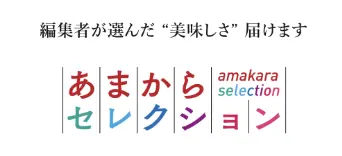
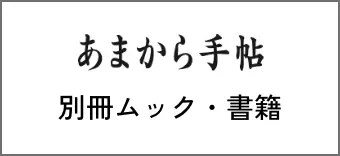















.jpg)
