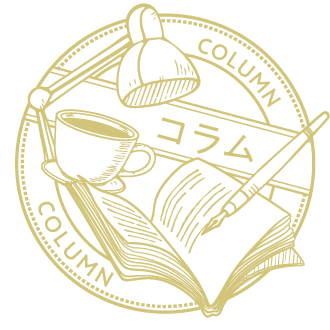「ソムリエ」の葛藤──美術家・森村泰昌
あの頃の“美味しいコラム”
あなたの好物はなんですかと問われ、「餅です」と答えると、たいていのひとは笑い出す。みんな、お正月に縁起物としてたまに食べたりはするのだろうが、ことさら餅が好きというのは、やっぱり珍しいようなのである。
父母がまだ生きていた頃のウチの朝食には、毎日餅が出た。思うに、あの頃のウチの朝食は、珍しいというよりもむしろちょっとヘンだった。
まずパンを食べる。菓子パンが多い。たとえば三色パン。これを三つにわける。父と母と私、このなかの誰が、餡、クリーム、ジャムの三色のいずれになるか、パンの外見からはわからない。私の本命はジャムなのだが、そうなるかどうかは食べてみてのお楽しみなのだ。いい歳をしたおとな三人によるそんなクイズ形式によってウチの朝食はスタートする。
パンのつぎはお茶漬けである。父は日本茶を商っていたので、おいしいお茶だけはいつも豊富にあった。そしていよいよ締めくくりとなる。ここで餅の登場となるわけだが、これを焼くのが私の重要な日課であった。
朝の食卓の中央にはいつも電熱器が置かれていた。ガスコンロやオーブントースターは使わない。若い人に電熱器といっても理解されないが、コイル状のニクロム線が迷路状に這いまわる電化製品で、このニクロム線に電気が流れると真っ赤に発熱して炭火の代わりのようになる。みりん干しやスルメを焼くのにも便利だが、鍋をするには火力が弱すぎる。
この昭和な電熱器に餅網を置き、餅を並べ時間をかけて焼く。餅の焦げぐあい、ふくらみかたなどを慎重に見きわめ、何度もていねいにひっくりかえし、こんがり焼いていく。焦げすぎたり、ふくらんだ餅同士がくっついてしまっては失格である。この作業は誰にも任せられない。ついに私は「餅焼きのソムリエ」と自称するようになった。とはいえその技を披露するのはウチの中だけだった。
以上は遠い昔の思い出である。父母も亡くなり、今はかつてほど餅を食べなくなった。しかしそれでも冷凍保存したエビ入りのピンク色をしたのし餅や、少々上等の米を使った真空パックの丸もちなどが常備されている。うどんに入れたり、茶碗蒸しの底にひそませたり、砂糖醤油をかけて海苔を巻く、あるいはきな粉をまぶしておやつとして食べたりもする。
ところでごく最近になって、新しい餅の焼きかたを覚えた。フライパンを使うのは邪道としりぞけてきた私だったにもかかわらず、此度は悔しくもフライパンを使用する。そしてこちらも許せないと拒否し続けていたガスコンロの火、これも活用してしまう。もちろんフライパンに直接餅をのせるだけでは、希薄で平凡な表情の焼き餅になる。電熱器による遠赤外線的な抑揚のある熱のはいりかた、あるいは加熱がまんべんなく行き渡らぬがゆえに生み出される、絶妙な焦げ模様の美学にもほど遠い。
ところが事前に餅を熱い湯で茹でたのちに、熱したフライパンにのせると、まるでつき立ての餅を焼いたかのようないい感じのふくらみと、それなりに納得できる焦げ目が容易に得られる。これはイケる、と自称「餅焼きのソムリエ」が言うのだから間違いはない。
しかしこの新発見の簡単レシピが、ウチの電熱器の出番をほとんどなくしてしまったというのも事実である。新旧の交替というものは世の必然であるが、それは何事においてもいささか寂しいものではある。
(「あまから手帖」2022年11月号 連載「あくまでも口福」より)

もりむら やすまさ●美術家。1951年大阪生まれ。京都市立芸術大学美術学部を卒業。1985年に自らがゴッホの自画像に扮する写真作品を発表。以降今日に至るまで、セルフポートレイトの手法を追求し続けてきた。近年の個展に、「M式海の幸―ワタシガタリの神話」(アーティゾン美術館)、「ワタシの迷宮劇場」(京都市京セラ美術館)など。2022年2月、人形浄瑠璃文楽の桐竹勘十郎との共演舞台「人間浄瑠璃・新鏡影綺譚」も大きな話題となった。