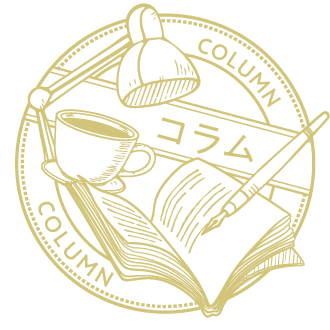イタリアの茹でジャガイモ──漫画家、文筆家、画家・ヤマザキマリ
あの頃の“美味しいコラム”
これまで暮らしたり、訪れてきた国々では、様々なものを食べてきた。今から45年前に香港の街中で食べたローストグース、14歳の時にフランスで食べた南フランス・ドーフィネ地方のチーズ、留学生活がスタートする初日にローマのレストランで食べたミネストローネ。ボランティアで滞在していたキューバで食べた豆の煮込みに、メラネシアの孤島で現地の人にふるまわれたコウモリのシチュー。
過去を手繰り寄せればあらゆる食べ物が出てくるけれど、私はグルメな味覚の持ち主ではないから、この世で食べられるものは何でも美味しいと思えてしまうし、何を食べたかよりも、その時自分はそこでどんな人と会い、何をしていたかといった事柄のほうが優先的に思い出されてくる。ひとつだけ確かなのは、前述のような記憶に刻印されている旅先での印象的な食事のほとんどが、あまり穏やかとはいえない状況下で食べたもの、ということだろう。
私にとって初めての海外旅行だった当時の香港はまだイギリス領で、街の環境も治安も今と比べると比較にならないくらい悪かった。道端に倒れる人を避けるように歩く人々。タクシーに乗ればドアを開けて物乞いをするボロをまとった子どもたち。「戦後の東京を思い出して辛い」と母は毎日戸惑い気味に呟いていたが、生きていくのに必死な様子の人たちを目の当たりにするのが初めてだった小学生の私にとっても、そういった光景はショッキングだった。
ある日母と一緒に街中に出かけてはみたものの道に迷い、狼狽(うろた)えているすきに彼女の腕からは大事にしていた腕時計が消えていた。スリ被害への怨嗟(えんさ)に肉体疲労、そして空腹で精神状態が荒(すさ)みきっていた母と、とりあえずそばにあった汚い飯屋に入って食べたのが、店頭に吊るされていたぺたんこのローストグースだった。「こんなところもう嫌」とぼやいていた母だったが、一口その肉を食べたとたん、血の気の失せていた彼女の顔色はたちまち赤みを帯び、表情も穏やかさを取り戻して元通りになった。私はそんな母を見てほっと安堵を覚えたものだが、そういった精神的効果が記憶の中でのローストグースの美味しさと結びついているのかもしれない。
貧乏だったフィレンツェでの留学時代も、食費に事欠くような毎日だったが、少しでもお金が手に入ると街中にある、ランプレドットという牛のモツの煮込みを挟んだパニーノを売る屋台へ赴いた。一口齧れば口の中はたちまちパンに染み込んだ煮汁とランプレドットの旨みで満たされ、この上ない幸福感に浸ることができたものだが、お金に困らなくなってから久々に食べたランプレドットからは、あの貧乏学生のころのような味覚による恍惚感を得ることはできなかった。
やはり画学生時代のとある真冬の日曜日、私と同様に毎日貧乏と格闘しながら、フィレンツェ郊外で古い家屋を借りて暮らしている画家の中年カップルを訪ねたことがあった。その時の私には交通費もなかったので途中までは自転車、その後はヒッチハイクという今思えば無謀極まりない移動手段で友人宅までの到達は果たしたのだが、彼らが昼食として用意してくれたのは、茹でたジャガイモに目玉焼きを乗せ、その上にパルメザンチーズを振りかけた料理だった。古い暖炉に薪をくべながら、毛布を被って頬張った茹でたてのジャガイモのうまさと温かさが体の隅々に染み渡り、至福の心地にしばし浸った。あれは、私が今まで食べた中でも世界で一番美味しいジャガイモ料理だったと思っている。
記憶に残り続けるこうした旅先での食べ物には、その時の境遇や一緒にいた人たちの思い出が、不可分な調味料となっているということだ。
(「あまから手帖」2021年7月号 巻頭連載「草枕 旅の味」より)
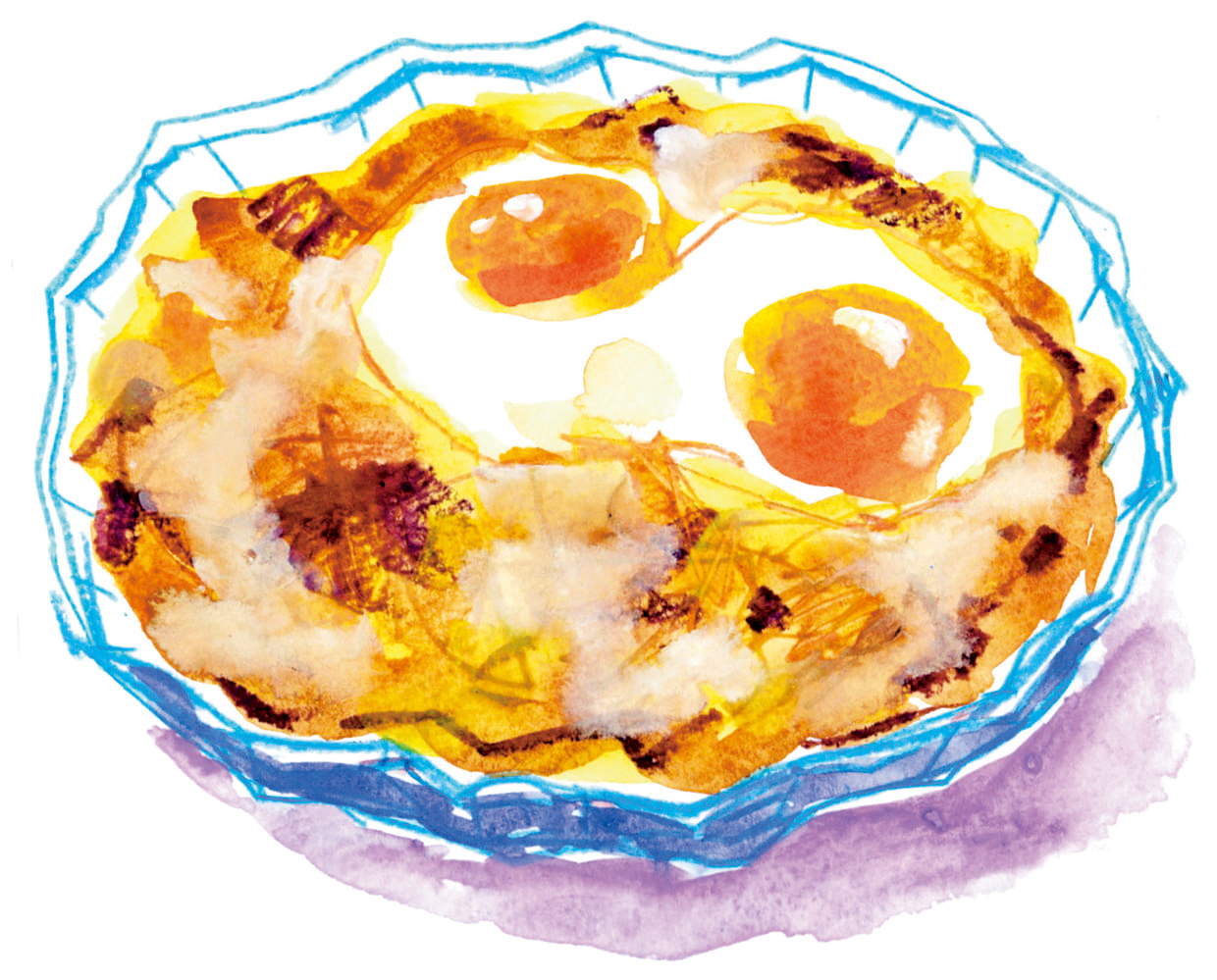

新装! 神戸・阪神間
三宮駅ビル新装で変わりゆく神戸・阪神間。新星レストランからテイクアウトまで、美味しいニュースをお届け。