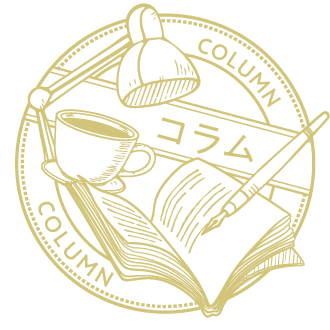剥がれた茶色のトゲ──作家、エッセイスト・平松洋子
あの頃の“美味しいコラム”
あじフライ。
かきフライ。
このふたつのフライは、私にとって双頭の鷲である。
そういえばずいぶん昔だけれど、ジャン・コクトーが戯曲と監督を手がけた『双頭の鷲』という映画があった。無政府主義者の詩人、スタニスラスが王妃を暗殺するために城に忍び込み、王妃に近づく。ところが、亡き夫と瓜二つの暗殺者に、王妃は言う。「あなたは私の運命よ。でも私はこの運命が気に入ったわ」。スタニスラス「僕たちは紋章の双頭の鷲となりましょう」。悲劇的な愛の始まりを演じたエドウィジュ・フィエールとジャン・マレーは、ため息が出るほど美しかった――。という記憶が飛来したのだが、しかし。
話はいきなり小さくなります。
鷲の衣について語りたい。
私は、あじフライ、かきフライから剥がれ落ちたトゲにたいそうな執着心を抱いている。フライ本体から落剥し、皿の上にばらばらと野放図に散らかった無数の茶色のトゲ。
世間には、パン粉をまぶして揚げた茶色い食べものがたくさんある。しかし、コロッケやメンチカツはともするとトゲの落剥率(=皿の上の残留率)が少なく、本体にくっついたまま口のなかへ運ばれがち。かにクリームコロッケは、衣と本体との一体感が強いし、エビフライなど、がぶりと端から食らいつくので剥がれようもない。
しかし、あじフライ、かきフライはちがう。バリッと揚げるからなのか、粗いパン粉のせいなのか、トゲの落剥率が高い。さらには、トゲにはあじやかきの気配が濃い。コロッケやメンチカツのそれとは一線を画す力強い存在感で、この信頼が揺らいだことは一度もない。
食べ進むにつれ、皿の上に茶色のトゲがばらばらと散らばり始めると、きたきた、と思う。ある破片はウスターソースにまみれ、ある破片は油の輝きをまとい、ある破片はせん切りキャベツの山裾に舞い降りている。もちろん、あえなく剥がれ落ちたり、自分が取りこぼした残骸だったりするのだが、もはやただの取りこぼしではない。
アチチと舌を焼くフライの興奮が鎮まりかけた終盤、儀式は始まる。
割り箸の先でしずしずと掻き集め、ひとところに移動させてトゲの小山をつくります。この作業は、あじが尻尾だけになりかけた手前とか、かきフライが残り1個に差し掛かったあたりで差し挟まれるのだが、割り箸を動かしながら、路上の落ち葉をかさこそ鳴らして動かす竹箒を思い起こしたりする。
ついさっきまでの散乱状態にカタをつけ、あらかたトゲを回収し終えると、湿気をほどよく吸い込んだ無口なひとまとまりが皿の上に現れる。濃茶色の雲間に走るせん切りキャベツ3、4本の緑の線は、さながら表現主義の絵画だ(いま筆が滑りました)。
準備が整ったところで、おもむろに割り箸でそっとつまむ。今度は取り落とさぬよう、豆ひと粒ほどの柔らかなそれを口に運ぶ段になると、私も呼吸を整えて朧ろな一点に集中する。
とりたてて言うほどのものでもない、吹けば飛んでゆく名もないしろもの。その奥まったところに、あじフライを、かきフライを、かつて衣だったときの熱や勢いや激しさを感じて、すこし遠い目になる。冷たいビールをごくり。
あえかな味に胸が震えるのだが、それもほんの一瞬のこと。かきフライはあと1個しかないのだし、あじフライの残りは、冷めないうちに尻尾まで急いで食べ尽さなければ。鷲はまだ吠えている。
(「あまから手帖」2022年2月号 連載「あくまでも口福」より)


エビ・マニア
多くの人が好きで、和食、中華、洋食…といろんなジャンルで楽しめるエビの総力特集。