
プロと共に食の最前線を学ぶ「関西食文化研究会」定期イベント
少し先の未来を思い描くことの大切さ
大阪ガス ハグミュージアムにて開催された、第42回定期イベントでは「代替食品NOW〜新技術と新素材の可能性に触れる一日〜」というタイトルで、「フードテック」がテーマ。あまから手帖編集顧問の門上武司の挨拶で開会しました。
トップバッターは米系ベンチャーキャピタル「Scrum Ventures」所属、『京都芸術大学』食文化デザインコースで講師も務める早嶋 諒さんの講演から。世界と日本の植物性たんぱくと培養肉の市場・企業紹介についての講話です。現在、世界的には人口増加中。将来的に起こり得るたんぱく質の供給不足への対策として研究開発が進んでいるのが、植物性たんぱく食品や培養肉です。すでに市場に出ているものとしてはアーモンドミルクや大豆を主原料とした大豆ミート。さらに世界の国々では、培養ウズラに培養シーフード、培養タマゴ、培養フォアグラなども実用化が進んでいるそう。日本国内でも開発が進んでおり、製造コストや味の問題など、今後さらなる改善が図られ、私たちの食卓に登場する機会も増えていくと予見されるという興味深い講話でした。
試食を交えて、実感しながらトレンドを知る
続いて国内の企業2社のフードテック最前線を各社の担当が登壇してのプレゼンテーション。話を聞くだけでなく、試食が付いているのも「関西食文化研究会」の定期イベントの楽しみです。
植物性油脂と大豆たんぱくを中心に事業展開する『不二精油』からは齋藤 努さんが登壇。23年に新規事業として創設したという風味基材事業より、動物性原料に頼らずに畜肉系や魚介だしの風味を再現する取組みについて紹介されました。
同社では、「人類の本能に迫る大胆な仮説」と「ヒトの感覚に頼る独創的なアプローチ」で作り出された独自のプラットフォーム「MIRACOA(ミラコア)」という概念と技術をもとに、植物性のものを食べた際に感じる物足りなさを、動物性のものを食べた時の満足感に近い感覚を持たせる、だしやスープの開発に挑んでいます。
植物性だしのニーズは、例えば健康上の理由で食に制限がある人。宗教上の理由で摂取しない人。菜食主義の人など様々な人々に必要とされます。また調理の現場においては長時間だしを引く必要がなく、時短にも。ビジネス面では海外への輸出が可能となること。また健康な一般の人においても、味が旨ければ日常的な選択肢の1つになり得るのではないかと思いを描き、開発を続けているとのこと。
植物性のだし「MIRA-Dashi」は業務用に販売を開始しています。チキン、ビーフ、カツオ、白湯、貝タイプはすでに商品化。開発中だというエビタイプのだしも試飲用に提供されました。試飲で配られた3種類のだしは、どれも動物性の素材を使わず、植物性だけとは思えない完成度の高さに驚かされました。
続いてプロの料理人にバトンをつなぎ、調理実演です。
登場したのは宮城県栗原市で、築200年の古民家を活用したオーベルジュ『風の沢 art & cuisine』を営む高山仁志さん。海外から来日した宿泊客の中にはベジタリアンやヴィーガンの方も多く、植物性のだしの必要性を肌で感じているとのこと。この日は2品の試食用の料理が振る舞われました。
プレゼンの後はコアメンバーを交えての意見交換の時間です。日本料理や中国料理のプロフェッショナルから、率直な発言が飛び出します。『辻調理師専門学校』吉岡勝美さんは、植物性だしは、精進料理の”もどき料理“のように使える可能性があるのではないかという意見。植物性タンパク質の市場の広がりに驚くとともに今後どのような展開を見せるのか注目したいなどの感想が。門上も「新しい技術をプロが使うとどうなるか?という挑戦が関西食文化研究会としても、大変意義深いことだ」と述べました。
キノコのメーカーが手がけるお肉!?
続いて今年『雪国まいたけ』から社名変更をした『ユキグニファクトリー』加藤真晴さんのプレゼンテーションです。初めに、マイタケやエリンギなどキノコの生産を通して研究を続けてきた野菜とは異なる菌類の栄養、免疫や健康に及ぼす効果などについての説明がなされました。
食料自給率が低い日本において、室内で栽培できるキノコは安定生産が可能です。その栄養特性を活かし、肉の代替食品として同社が開発した商品が『キノコのお肉』です。といっても原料はマイタケで、その繊維質を活かした、肉のような食感が特徴となっています。低脂質、低糖質で食物繊維がたっぷり。加熱は不要でそのまま食すことができ、肉の代わりに様々な料理に取り入れることができるそう。参加者には試食用に『キノコのお肉』が配られました。
こちらを用いたプレゼンテーションは日本料理から『靱本町 がく』今川 岳さんが登場。実演したのは『キノコのお肉』と夏野菜を混ぜ込んだ具沢山のひろうすです。肉のようで原料はマイタケ。その質感を活かした、食べ応えのあるお椀を披露しました。
木綿豆腐と山の芋、卵白をすり鉢で混ぜ合わせた中に、さいの目に切った夏野菜と、『キノコのお肉』を混ぜ合わせて揚げたひろうすを披露しました。吸い地も乾燥させた干マイタケを戻して煮出しただしと昆布だしに醤油と塩で味を整えて。
食感が特徴的なひろうすは、噛むたびに様々な旨みが溢れ、滋味深く美味しい一杯です。和食の料理人が新素材を使って仕立てた精進の椀に試食した参加者からも感嘆の声が。このような、店では味わえない挑戦的なレシピが披露されるのも「関西食文化研究会」に参加する醍醐味です。
コアメンバーの視点や意見も参考に
定期イベントでは、料理業界を牽引する名だたる料理人たちがコアメンバーとして毎回参加します。この日は『神戸北野ホテル』の山口 浩シェフ。京料理『木乃婦』の髙橋拓児さんも来場。それぞれの現場での経験をもとに様々な切り口での意見が聞ける貴重な機会となっています。
次回の定期イベントは2026年2月の開催を予定しています。会員登録すると、過去のイベントレポートなどを会員限定サイトにて閲覧ができるので、ぜひご入会ください。
【組織名】
関西食文化研究会
【詳細】
https://www.food-culture.jp/
※入会金・会員登録は無料。
recommend






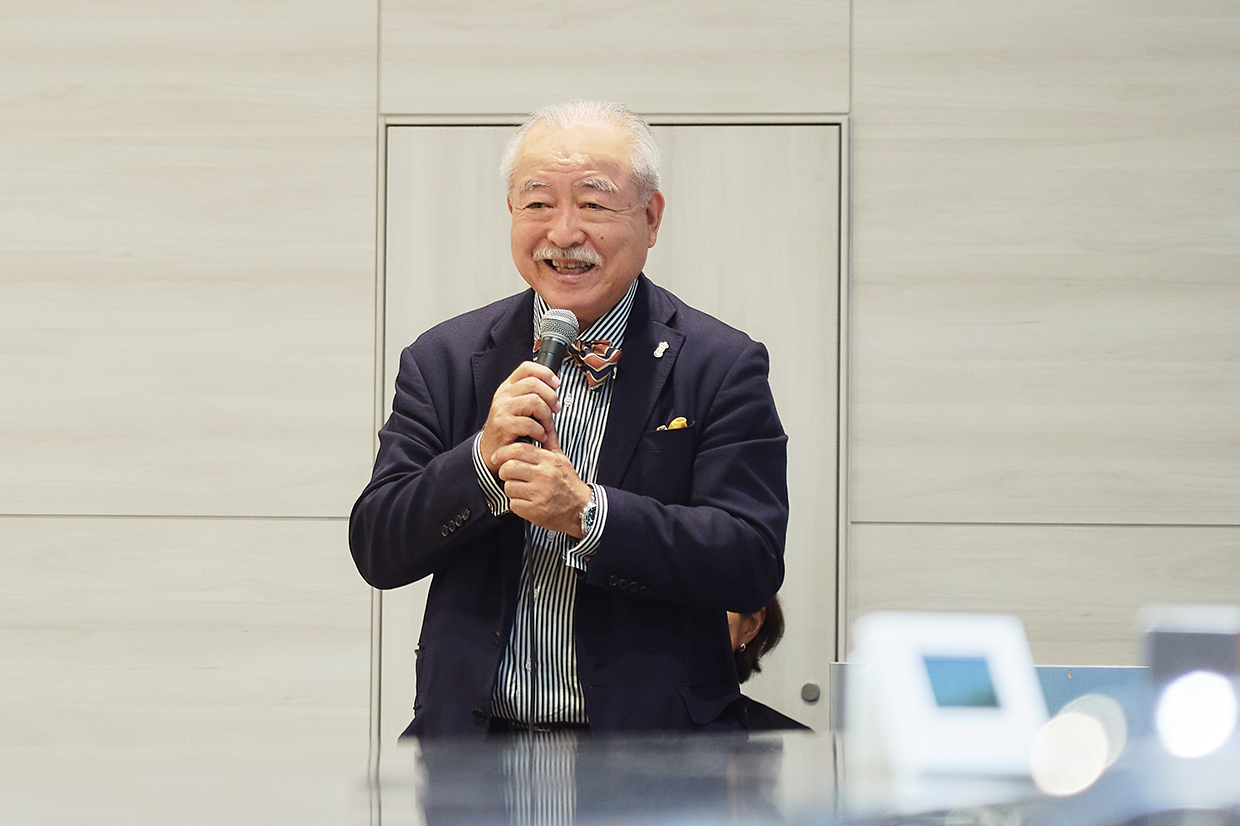



















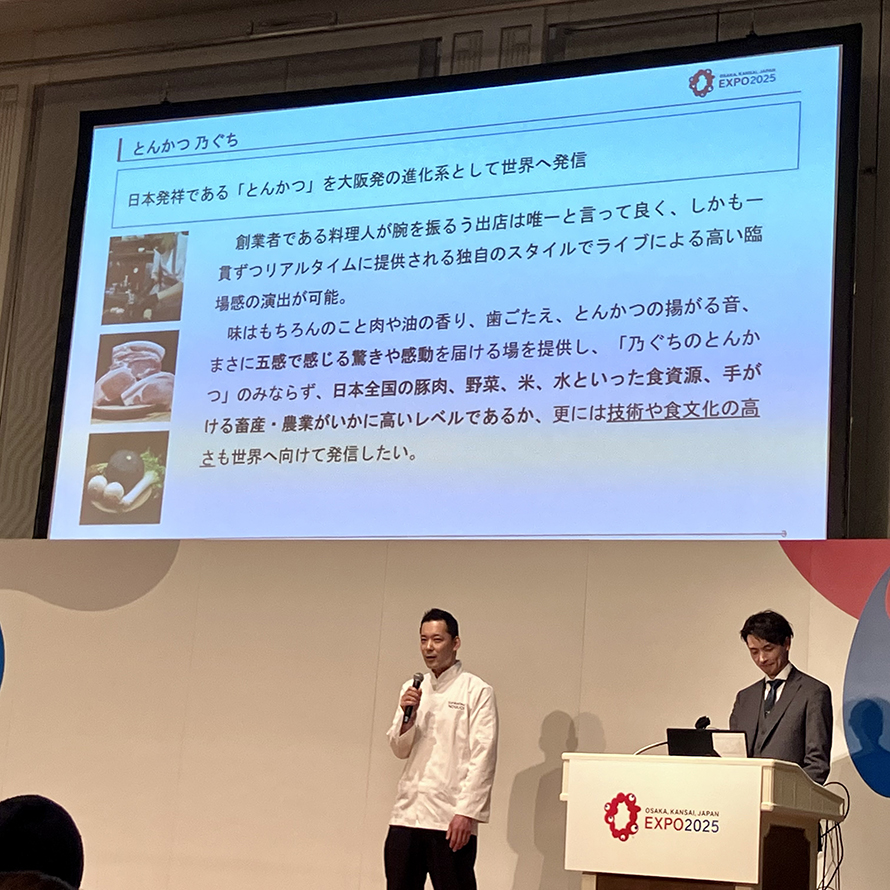
.jpg)

