
土地の記憶をもつ「在来種」が万博にもたらす“違和感”/『タネト』奥津 爾さん
「食を通じて、いのちを考える」ことをコンセプトに、空間を“空想のスーパーマーケット”に見立てた展示が展開されている。
「EARTH MART」で観客たちを最初に迎えるのは「いのちのフロア」。毎日口にしているものを通して、感謝の気持ちが生まれるような演出となっている。
今回、「いのちのフロア」の入り口を飾る作品「野菜のいのち」を手掛けた奥津 爾(ちかし)さん(オーガニック野菜の直売所『タネト』店主)を取材した。
“未来”を展示する万博で、奥津さんが示したのは、長崎・雲仙の地で育まれてきた在来種の野菜たちだった。
土地の記憶を持つ野菜たち
6月下旬の某日、万博開園の2時間前。
その日、黒田五寸人参(くろだごすんにんじん)の種が作品に加わった。種といっても粒状ではなく、ギュッと詰まったさやに入っていて、花の名残を留めている。
これは、ある一人の農家によって育まれた、40余年分の土地の記憶だ。
「EARTH MART」の入り口がバーンッと開くと、最初に目に飛び込んでくる作品「野菜のいのち」。
雲仙の在来種(※)の野菜、40種以上の野菜がダイナミックに展示されている。種もあれば、花や実、朽ちる直前のものまで、その時期はいろいろ。
作品を手掛けたのは、長崎・雲仙でオーガニック野菜の直売所『タネト』を営む奥津 爾さんだ。
もともとは夫婦で、東京・吉祥寺で風土と身体に根ざした食堂と料理教室をしていたが、雲仙で40年以上にわたり在来種の種を繋いできた農家・岩﨑政利さんとの出会いを機に、2013年より移住。
在来種・固定種の野菜を軸とした、野菜の直売所として『タネト』を開設、さらに種と農を基盤として未来を創造する「種を蒔くデザイン展」「種と旅と」「THE BLUE HABEST」など様々なイベントを企画している。そのローカルな活動は全国へと波及。料理人や著名人などとも幅広いネットワークを持ち、海外からも注目を集める人だ。
万博に展示された「野菜のいのち」は、奥津さんが尊敬する岩﨑さんの畑の農作物だけで構成。空間デザイナーの佐藤寧子さんと共に作品を作り上げた。会期中、“いま現在の畑”のものをリアルに持ち込み、雲仙の季節、風土を伝えている。
※普段我々がスーパーで目にしている野菜の多くは、1回限りの収穫を目的として品種改良された「F1種」。これに対し、種を採って蒔けばまた同じように収穫できる「固定種」がある。「在来種」とは、特定の地域に一世代(20年~40年ほど)以上、ずっとその土地で自家採種されてきた野菜のこと。
野菜にも種があり、芽が出て、花が咲き、また種ができる。
スーパーに並ぶ野菜から、この植物の営みを想像するのは難しい。作品を眺めていると、生命の循環の輪のなかで、普段目にしていた野菜が、いかに一瞬の姿だったかに気付かされる。
「岩﨑さんが初めて自家採種したのが、黒田五寸人参。なのでこれは43、4年目なのかな。だからこれが、岩﨑さんの畑を一番象徴しているものですね」。奥津さんはそう言いながら、黒田五寸人参の種を見せてくれた。
「岩﨑さんが人生をかけて継いできました。毎年種を採るって、要はその年のことを種が記憶として蓄積していくってことなんです。例えば、その年大雨が降ったら、その雨のデータを種が遺伝子に全部記憶しているんですよ。だから、ここには、40年分の雲仙の風土が全部詰まってるんです」。
「違和感を持って帰ってほしい」
メッセージ性の強い作品を作りながらも、奥津さんが伝えたかったことは意外にもシンプルなものだった。
「一番は、違和感かな。なにこれって思ってもらいたいですね」と。
「万博って、いわば未来の見本市じゃないですか」と続けた奥津さん。
埋立地の夢洲に、先端技術や映像が集う万博のなかに、圧倒的な有機物を入れたかったのだという。何十年も前からある在来種は、一見、未来と対極のようにも思えるけれど、本質的な原点でもあるということ。
この地で有機物がもたらす違和感は、私たちに不思議と心地よい安心感も与えてくれる。
「これですべて伝えられるなんて思ってない。
でも、もしかしたら子どもたちが、あれはなんだったんだろうって、野菜の種や自然の営みに興味を持ってくれるかもしれないじゃないですか。
だから、どんなに近くで見ても美しい、自然の造形美を感じてもらえたら」。
在来種は均一ではない。形もいびつで、大きさもバラバラ。だからこそ、ずっと見ていても飽きない面白さがある。
「子どもたちに感じてほしいことがもう一つあって。在来種って、我々そのものなんですよね。世の中は規格化されたもので溢れているのに、“個性”を求められる。子どもたちに、多様性も感じ取ってもらえたら嬉しいですね」。
在来種はノスタルジーじゃなくてリアル
奥津さんは、決してF1種を否定しているわけではない。
数が少なく、安定的ではない在来種だけでは、日本で1億人の人口を自給するなど不可能だ。在来種とF1は補完し合うものであってほしいと語る。
「本来、各地に残る郷土料理は、在来種の野菜で作っていたものなんです。在来種は食文化そのものであり、一度途切れてしまったらもう復活できないんです。
在来種を食べるということは、その土地の風土を食べるということ。ときどき、 “ノスタルジー”として語る人がいるけれど、在来種は現代に残すべき食文化として貴重だし、なによりおいしいものなんです」。
さらに、食文化とは別に、現代における在来種の重要な側面として「食料危機のリスクヘッジのためにもめちゃくちゃ大事」と奥津さんは語気を強めた。
「現在日本で使われているのは、種だけに限らず、農薬や化学肥料もほとんどが海外産なんですよ。だから、もし輸入に頼れなくなったとき、農薬などを使わずに自家採種している農家が各地にいれば、その人から未来を繋げるかもしれない。これは、ノスタルジーじゃなくて現実なんです」
初めてこの作品を見たとき、スカスカで、網目のような繊維だけで形を保っている“最期の大根”が、ずっと頭のなかに残っていた。
よく煮込まれた大根に見られる、あの細い繊維の部分だけが残っている感じの。その朽ち切った静かな佇まいが、何ともかっこよかった。
思えば、あれが奥津さんの仕掛けた違和感だったのだ。
data
- イベント名
- 2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)
- 住所
- 大阪府大阪市此花区夢洲
- 場所
- EARTH MART

writer
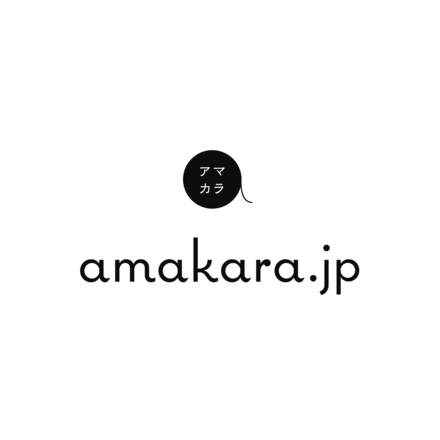
amakara.jp編集部
amakara.jp
関西の食雑誌「あまから手帖」(1984年創刊)から生まれたwebメディア「amakara.jp」を運営。カジュアル系からハレの日仕様まで、素敵なお店ならジャンルを問わず。お腹がすくエンタメも大好物。次の食事が楽しみになるようなワクワクするネタを日々発信中。
recommend



























