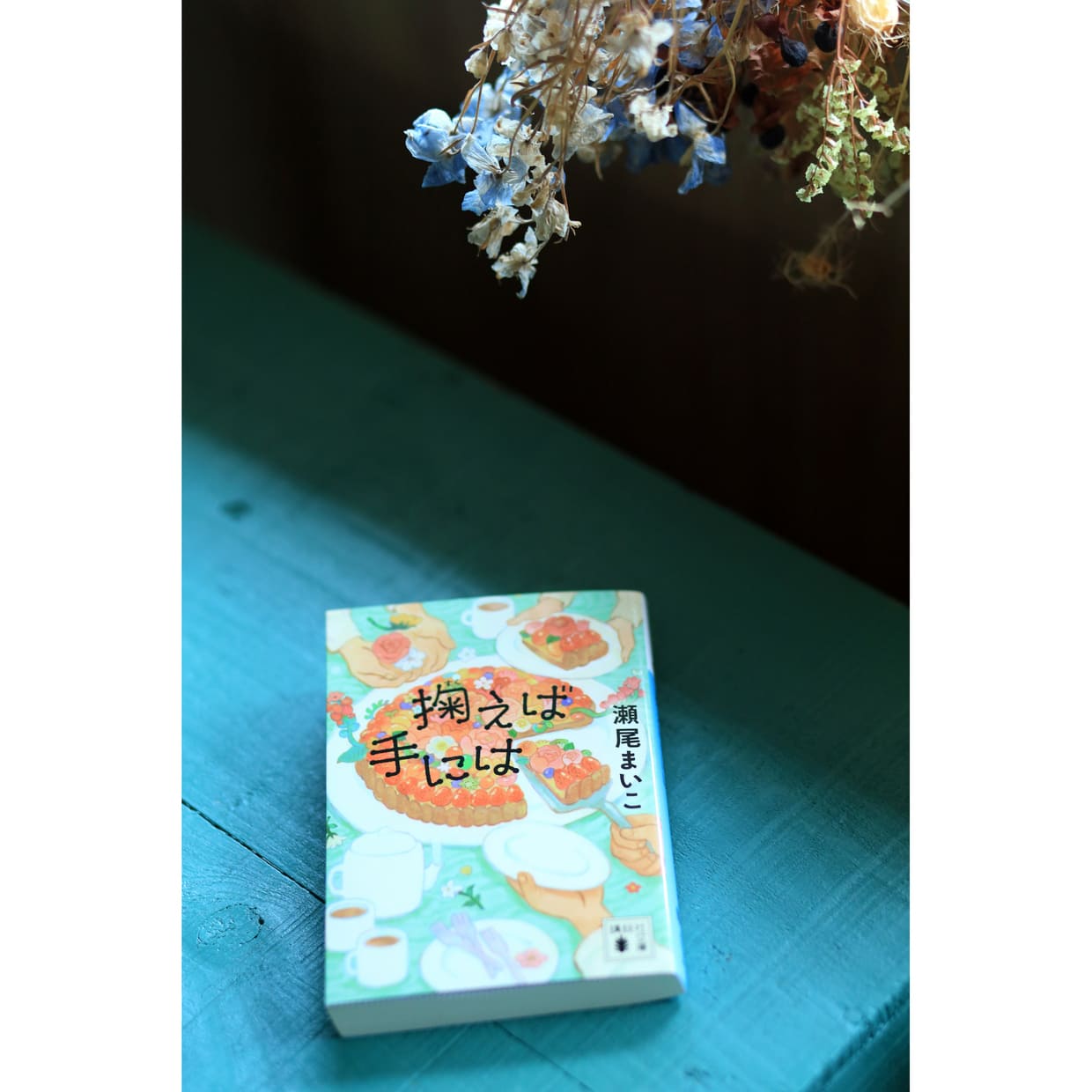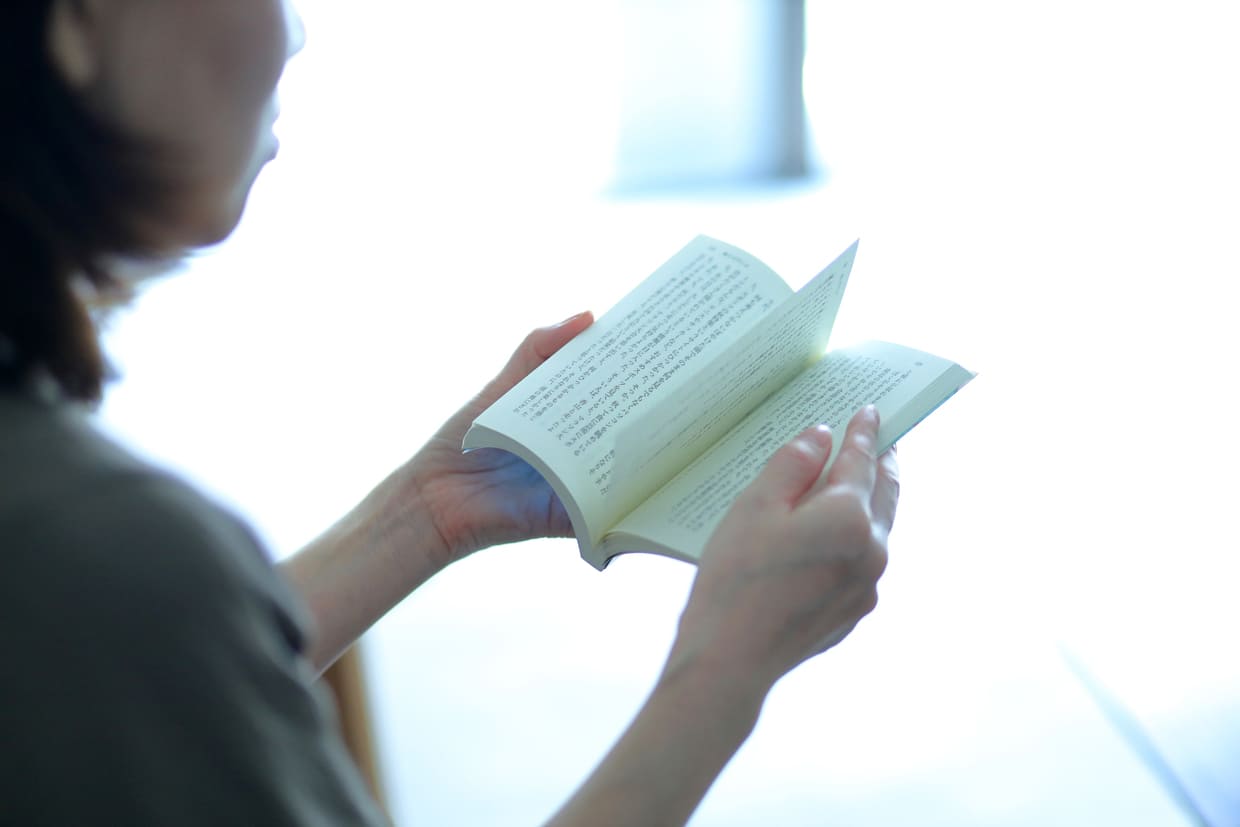瀬尾まいこさん【前編】誰もが、煌めくものを必ず持っている。小説『掬えば手には』
平凡で取り柄のない青年が、ある日「人の心が読める」特殊能力があると気づき、関わる人の心に寄り添っていく、どこまでも温かくて優しい物語です。舞台は、街の小さなオムライス屋。ストーリーが動くとき、いつもおいしいものがそこにあります。
著者である作家・瀬尾まいこさんに、前編では今作への思いを、後編では瀬尾作品に度々登場する“家族”をテーマにお話を伺いました。
contents
平凡な主人公の、秀でた能力
――ハードカバーの黄色いシンプルな表紙とはガラリと雰囲気が変わり、文庫本ではおいしそうなタルトが表紙になりましたね。
- 瀬尾さん(以下、瀬尾):
- そうですね。ちょっと不思議というか、ファンタジー感も出て、可愛くて気に入っています。
――主人公の梨木君は、平凡であることがコンプレックスという、多くの人が一度は抱える悩みを抱えた青年です。彼のような人を書こうと思ったきっかけを教えてください。
- 瀬尾:
-
書いたのは単行本の時で結構前なので、正確かわからないんですけど(笑)。
大体の人はみんな普通ですけど、でも、なにかしらの特技ってあるじゃないですか。特技とまでは言えなくても、誰もが秀でたところ、何か煌めくものを必ず持ってるから、それを思って書き始めました。
――平凡さに悩んでいた梨木君ですが、「実は人の心が読めるんじゃないか」と、自分の特別な能力に気が付きましたよね。
ところが、バイト先に入ってきた常盤さんは、心が全く読めないミステリアスな人でした。彼女は梨木君にとってどんな存在だったのでしょう。
- 瀬尾:
-
彼は、人の心が読めることが自分の能力だと信じて、それにすがって生きているわけですが、それは決して特別な能力じゃなく、普通のことじゃないですか。
誰でも人の心は読めないけれど読もうとしますよね。
だから、彼にすごいところがあるとしたら、「あの人は今こう思ってるんだな、じゃあこうしてあげよう」って、行動に移せること。これだけが彼の性格の秀でたところなので、普通の男の子なのだけれど、本当にすごいところを出してあげようと思いました。
――それで、それまでやや曖昧(あいまい)だった能力が、常盤さんを通して本当に目に見えない力、他の人には聞こえない声を聞く力が、梨木君に強く宿っていくわけですね。
- 瀬尾:
- そうですね。それは、彼が人の気持ちに常に敏感に、思いを巡らせていたからこそ聞こえるようになったんじゃないかと思います。
――常盤さんとは対照的に、梨木君のバイト先であるオムライス屋の店長・大竹さんは、口も性格も最悪ですが、梨木君にはそれは臆病さの裏返しだったり、心根の優しいところが見えていて。読んでいたらだんだん大竹さんが可愛くなっていきました。
- 瀬尾:
-
私の作品には悪人が出てこないというのは、常々言われていること。
だからとちょっと悪いヤツを出そうと思ったんですけど、やっぱり人って可愛い部分が出てしまうじゃないですか。最後には、「頑張って悪ぶってはるんやなぁ」と思いながら書いていました(笑)
でも、私が大竹さんの店のバイトだったら、1日で辞めたくなると思います。だけど気が弱いから、辞めるって言えへんし、仮病を使うしかないですね(笑)
玉子好きから、物語の舞台が決定
――梨木君以外のバイトが続かないほど性格の悪い大竹さんなのに、作るオムライスは絶品なんですよね。本当においしそうでした。なぜ、オムライス屋を舞台にしようと?
- 瀬尾:
- 私、玉子料理が好きなんですよ。天津飯、親子丼…あ、鶏肉は苦手だから玉子丼か。あとオムライスが好きなので、オムライスにしました。
――そういえば、過去の作品『そして、バトンは渡された』でもオムライスにまつわる印象的なシーンがありましたね。
- 瀬尾:
-
ありましたね、ケチャップで(熱い)思いをダイイングメッセージのように書く場面。オムライスそのものに強い思い入れとかは全然無いんですけど、すみません(笑)。
でも、誰が作ってもそこそこおいしく作れるっていうところもいいですよね。
――オムライスに限らず、作中には食べ物がたくさん出てきますよね。梨木君主催でバイト先の大竹さんや常盤さんと親睦を深める際に、誕生日ケーキを用意するシーンとかも温かくて。
- 瀬尾:
-
誕生日ね、人を祝える大チャンス! いいですよね、誕生日ケーキ。
最初は、どうしたら常盤さんが来てくれるかなって思って入れたエピソードだったんですが。でもそうやってみんなでケーキを囲むと、なんとなく、そこにいつもと違ういい感じの空気ができたんだと思います。
――特にお好きなシーンはどこですか?
- 瀬尾:
- 最後の方は気持ちが良かったですね。私は綿密に考えてから書くタイプではなくて、話を書きながら、登場人物たちと一緒に進みながら「へぇ、そうなるんだ」って書いていくタイプなんですが…
――ゴールを決めずに書くんですか?
- 瀬尾:
-
決めてしまうと、書くの面白くないじゃないですか。
だからこの作品も、最後に登場人物たちの言葉や過去の出来事を書き進めていくうちに、私自身も「そういうことだったのか」って皆さんの気持ちがわかって気持ち良かったですね。
主人公が掬うものとは
――「掬えば手には」というタイトルですが、本作に「掬」という字が使われたのは1度だけだと思うのですが…。
- 瀬尾:
- そうだったと思います。普通はヘルプ(救う)の方ですが、苦しみの中にいる常盤さんを「掬う」ときに、彼女がガラスか何かのなかにいて、掬い上げるイメージで使いました。
――「掬えば手には」の後に続く言葉って考えたりしたんですか?
- 瀬尾:
-
えー、掬えば手には…。そうですね、手に残るものは人それぞれ違うけど、掬わなかったら何もないし、何も握っていないのは寂しいじゃないですか。でも、ほったらかしにしないで、ちょっと掴んでみたら、掬おうとしてみたら、100回中3回、5回くらいはなにか絶対に光るものがあると思うんです。
このお話の「掬う」は、梨木君が掬った声や掬った動作であり、心が読めるというのも、彼が掬おうとしているからですね。
大竹さんも、めちゃくちゃおいしいオムライスで、常盤さんを掬ってあげていたのかも。
――そういえば、オムライスもスプーンで掬って食べますもんね。
- 瀬尾:
- たしかに!
――え、狙ってないんですか?
- 瀬尾:
- 狙ってないです(笑)
―-書きながら登場人物を理解していくという瀬尾さん。ゴールは決めずに書くけれど、「幸せになってもらいたい」と思いながら進めていくのだとか。キャラクターについて話すとき、まるで実在する人かのように、客観的にみて個々を尊重しているのが伝わってきました。
文庫本には、本編に登場した人物たちの、その後の話も収録されています。ぜひご覧ください。
瀬尾まいこさん【後編】「おいしいものと、人がいること。どちらも幸せの象徴です」に続く。
profile

小説家
瀬尾まいこ
小説家。京都で中学校の国語教師をする傍ら、執筆活動をスタート。2001年、26歳のとき「卵の緒」で第7回坊ちゃん文学賞を受賞し、作家デビュー。2011年に教員を退職し、専業作家へ。多くの代表作を持ち、「幸福な食卓」(吉川英治文学新人賞)、「天国はまだ遠く」「僕らのごはんは明日で待ってる」、「そして、バトンは渡された」(本屋大賞)、「夜明けのすべて」など、映画化も多数。家族愛や人とのつながりを丁寧に描いた温かな作風に、年齢を問わず多くのファンを持つ。

この記事を読んだ人におすすめ!
大阪の街の本屋さん『正和堂書店』の選書コラム「ブックカバーはごちそう」でも、『掬えば手には』をご紹介しています。 併せてご覧ください。ほかにも心に効く本揃ってます!
recommend