
京都【引千切】実は宮中由来の高貴な雛菓子の話
contents
宮中の高貴な菓子から京都・雛菓子界のスターへ
よもぎを混ぜて草色にしたり、ピンクに色づけした餅やこなしで掌のような形を作り、少しくぼませた中心部分に餡玉やそぼろ状の餡を乗せる。店や作り手によって趣きは異なるものの、雛祭の時期にだけ出回るこの生菓子は「引千切」と呼ばれている。
そもそものルーツは、宮中で誕生や御着帯の儀式を行う際に誂えられた、平たい餅に餡を乗せる「戴餅(いただきもち)」。子どもの生育を祝う餅であったことから女児誕生の贈りものになり、やがて雛の菓子として作られるようになったと言われている。引きちぎったかのフォルムであることから「ひっちぎり」とも呼ばれていたが、いつしか「ひちぎり」になり、今は主に「引千切」と表記される。アコヤ貝の形に似ているため「あこや」とも呼ぶところもあり、由来についても諸説あるようだ。
とはいえ、半世紀以上前は京都でもそんな雅な雛菓子があることは庶民には周知されておらず、桃の節句の菓子の主役はあられや三色団子だった(と思う)。段飾りの一隅に置かれた三色の菱餅はあられや団子よりやや格上で、母の「硬うなる前に焼いて、砂糖つけて食べよか」の一言にきょうだいで目を輝かせた記憶がよみがえる。
一方、格調高い茶席や一部上流家庭の雛菓子として密かに愛でられていた引千切は、バブル期にメディアで紹介される機会を得て、今や雛菓子界の大スター。老舗の菓子司からカジュアルな餅菓子屋さんまで、時にはスーパーの和菓子売り場に並ぶこともめずらしくないメジャーどころに成長した。他府県では菓子名すら聞いたことがないと言う人も多いようだが、京風を標榜する和菓子店ではちらほら見かけるようになっている。
世が世なら庶民には無縁だった雅な和菓子。全国区になる日も近かったりして?
writer
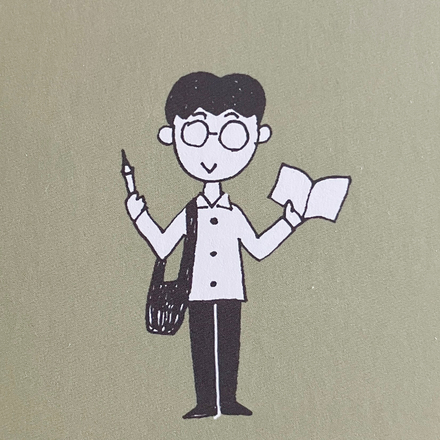
小林 明子
kobayashiakiko
京都在住フリーライター。缶入りクッキー、ワッフル、薯蕷饅頭、そば餅…、これらの名店に徒歩で行ける京都市の烏丸御池近くに生まれる。自動的に甘いもの好きが出来上がりました。
recommend


















