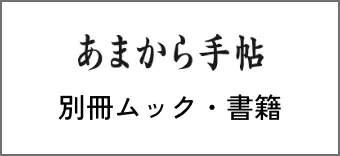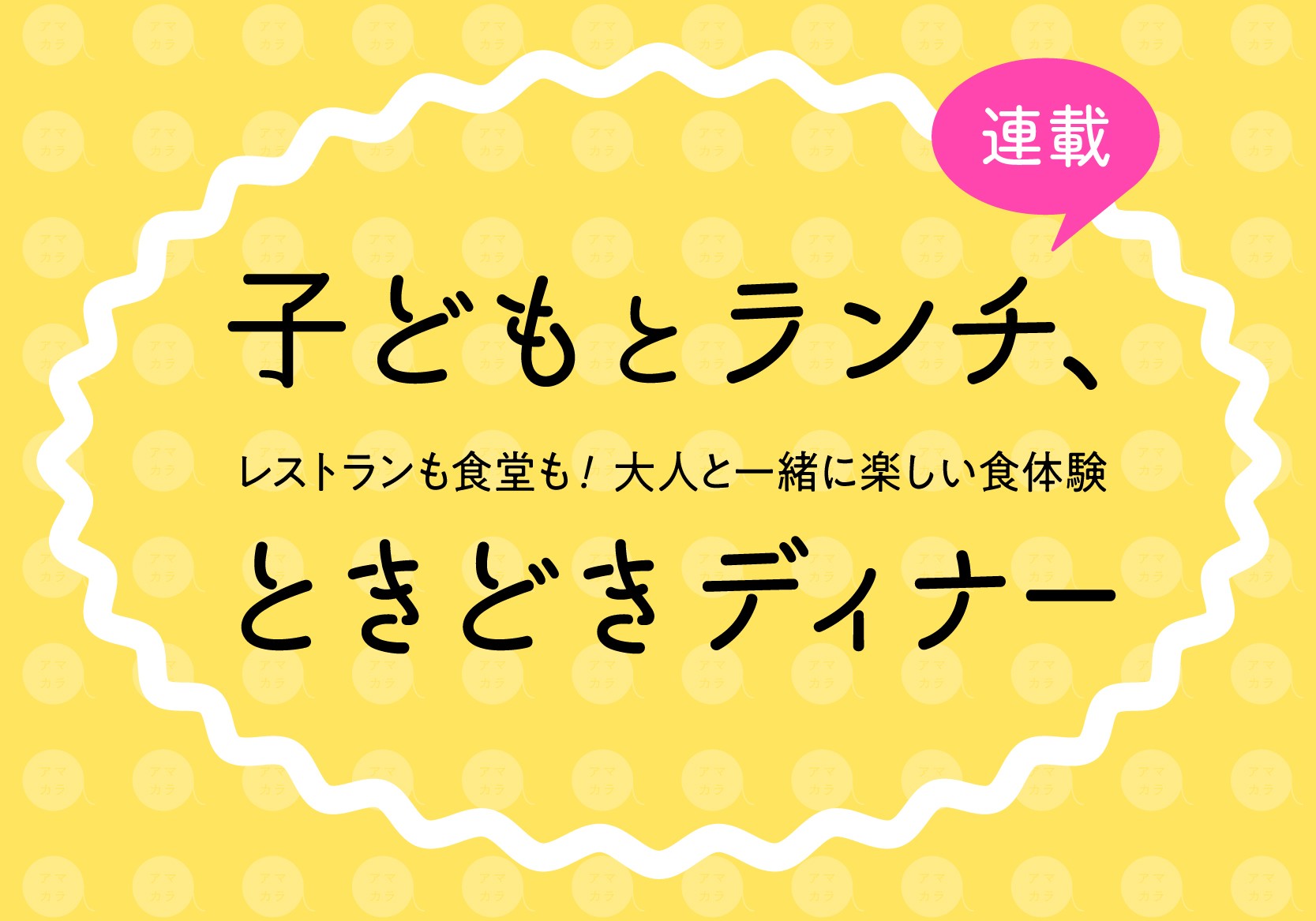達人のジビエ──大阪『ジュンジーノ』の「山鶉のローストと煮込み」
contents
シェフ自ら、デクパージュ
木のトレイに、山ウズラの塊肉。脇に添えたのは、モモ肉の煮込みだ。焼き野菜に、ジャガイモのチップス。まずは、その姿をカウンターで披露し、目にも止まらぬ速さで胸肉を切り分け、皿に盛って内臓のソースをかける。八島淳次シェフのデクパージュは、名人芸の域だ。
お客様の前で、料理を切り分けて皿に盛るデクパージュは、本来、ホールの仕事。日本の町場のレストランではすっかり見かけなくなったけどね。僕は北イタリアで修業して、本物のジビエを学んで帰って来た。塊肉でしか出せない美味しさを知っているし、それを味わってほしいから、うちのジビエにはデクパージュが欠かせないんですよ。
イタリアに渡ったのは、23歳の時。修業を始めたピエモンテが、八島シェフの運命を決めた。ミラノやベネチアのレストランでも働き、フィレンツェの3つ星『エノテカ・ピンキオーリ』では、モダンな郷土料理の洗礼を受け、ワインにも開眼。そのすべての経験が、帰国後は北イタリアの料理で勝負したい、という想いへと繋がり、4年の修業の最後にもう一度、ピエモンテに戻ったという。
トマトが嫌いやったから、北に行ったんやけどね(笑)。ピエモンテの食文化に魅せられて。
他の土地の料理も学ぼうと何店舗かで働いたけど、有難いことに行く先々で前店のシェフから「ジュンジーノをよろしく」と連絡が入ってて。貪欲やったし、負けん気も強かったせいか、当時の日本人としては稀有な体験をさせてもらった。
『ピンキオーリ』時代は、20代の若造のクセに高級ワインをブショネやと突っ返したり(笑)、カトラリーに調度品、デクパージュと何でも知りたがりやったから、「ワインやホールのことまで興味を持った日本人はお前だけや」って、逆に認めてもらって。3年が過ぎた頃、『ピンキオーリ』での学びを北イタリア料理に生かしたいという想いが固まって、最後にもう一度、ピエモンテに行ったんです。
本場のジビエを体得した自負
苦楽園に『オステリア・エノテカ・ダル・ジュンジーノ』を開いた1989年。関西イタリアンはブーム前夜だった。手打ちパスタも、ジビエも、ワインとのマリアージュも認知されていない中、カーブに名だたるイタリアワインを備え、北イタリアのトラディショナルな料理を展開。美食家の心を鷲掴みにしつつも、“トマトを使わない茶色いイタリアン”は異端視され、当時の八島シェフは孤軍奮闘だった。
ジビエはおろか、セコンドピアット(メイン料理)を食べてもらうのに、どんなに苦労したか。当時はまだイタリアンといえばパスタやピッツァで、コースで愉しむ概念すらなかった。20代やったからできたんでしょうね。オレは本物を伝えるんだ!と躍起になって、思いっきり“イタ飯ブーム”に逆行してました(笑)。あの頃はイタリアで修業しても、パスタ場までいったらいい方やったけど、僕はセコンドピアットを任され、ジビエを扱えるようになるまでは帰らないと決めてた。山間部の北イタリアで体得したジビエは、間違いなく、僕のスペシャリテです。
今回のワンデッシュは、八島シェフ曰く「ジビエの入門編」。白身肉の山ウズラは、比較的淡泊でクセがない。胸肉はローストにして持ち味を率直に楽しませ、モモ肉は煮込みにして力強い旨みを際立たせる。内臓のソースに忍ばせたのはドライイチジク。これが、八島流の野鳥ジビエのスタイルだ。
現地で覚えたのは丸ごとローストする手法。でも、それだとモモ肉の火入れが浅くなるので、外して煮込みにしました。ジビエは丸ごと使うのが定石やから、捌いたら細かい骨まで全部のガラを使い、モモ肉と共にブランデーや赤ワインで3時間ほど煮込みます。一度漉して、ブイヨンとドライイチジク、砂肝やレバー、心臓などの内臓を加えて火を通したら、ミキサーにかけてソースに。ピエモンテでは内臓のソースに果実を使わないけど、トスカーナでは使っていたから、僕なりのアレンジを加えたワケです。
職人シェフ、新たなカウンターへ
茶褐色の艶めくワンデッシュは、まさに八島シェフの真骨頂だ。しっとりと火入れした胸肉の繊細な旨みと相反する、モモ肉の煮込みの芳醇さ。内臓のソースは鉄分由来の複雑味にドライイチジクが利いていて、どっしりと重厚な中にチャーミングな果実味を感じる。エレガントな野趣味だ。
僕がイタリアで学んだことは、郷土の料理をどうモダンに仕立てるか、ワインとどう合わせるか。そのためには、風土を知り、食文化を吸収しないといけない。ワインについても同じです。帰国してからも、向こうで買った料理書をボロボロになるまで読み込んで、ワインの知識もアップデートして、イタリアを学び続けてきた。もうね、僕は半分イタリア人やと自負してますよ。
八島シェフは、苦楽園、神戸の元町、淀屋橋などでレストランを営み、イタリア食文化の教鞭を取ったり、商品のプロデュースも手掛けてきた。その濃い料理人人生の45年目、2019年に開いたのが西天満の『ジュンジーノ』だ。人生初のカウンター。手と口を同時に動かすのは、さぞ難しかったのでは?
イタリアの厨房では、しゃべりながら調理するのが日常で。話すと手が止まるようなヤツはダメだと言われて(笑)、鍛えられましたから。今はカウンターにしてよかったと思ってます。時代が変わってコース主体の世の中になったでしょ。そうすると、カルボナーラみたいな料理が食べられなくなったってイタリアン好きが嘆くんですよ。それで、コースの予約がない日や、コースのお客様がお帰りになった後の時間に、アラカルトを始めました。今の店は年内で閉めますけど、大阪市内で必ず再開します。その時もまた、カウンターにして、アラカルトもやりますよ。次の店が、僕の集大成になると思います。
インタビューの最後に、八島シェフは言った。「商売人ではなく、職人でいたい」。手打ちパスタを広め、イタリアワインの普及に努め、ジビエを根付かせた関西イタリアン界の功労者は、63歳で次のステージへと向かう。カウンターで軽妙なトークを繰り広げながら、職人シェフとして生き続ける。
data
- 店名
- ジュンジーノ
- 住所
- 大阪府大阪市北区西天満4-12-12 シーサX SHISA梅新東ビルB1
- 電話番号
- 06-6365-8008
- 営業時間
- 12:00~(前日までに要予約)、18:00~21:30LO(予約制)
- 定休日
- 日曜
- 交通
- JR北新地駅・各線淀屋橋駅から徒歩7分
- 席数
- カウンター8席、テーブル4席
- メニュー
- ランチコース6600円~、ディナー8800円~。グラスワイン1320円~、ボトルワイン8800円~。
- 外国語メニュー
- なし

writer

中本 由美子
nakamoto yumiko
青山学院大学を卒業し、料理と食の本を手掛ける東京の「旭屋出版」に入社。4年在籍した後、「あまから手帖」に憧れて関西へ。編集者として勤務し、フリーランスを経て、2010年から12年間、編集長を務める。21年、和食専門ウェブ・マガジン「和食の扉〜WA・TO・BI」を立ち上げ、25年に独立。フリーの食の編集者&記者に。産経新聞の夕刊にて「気さくな和食といいお酒」を連載中。
recommend