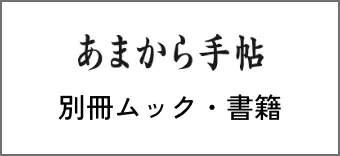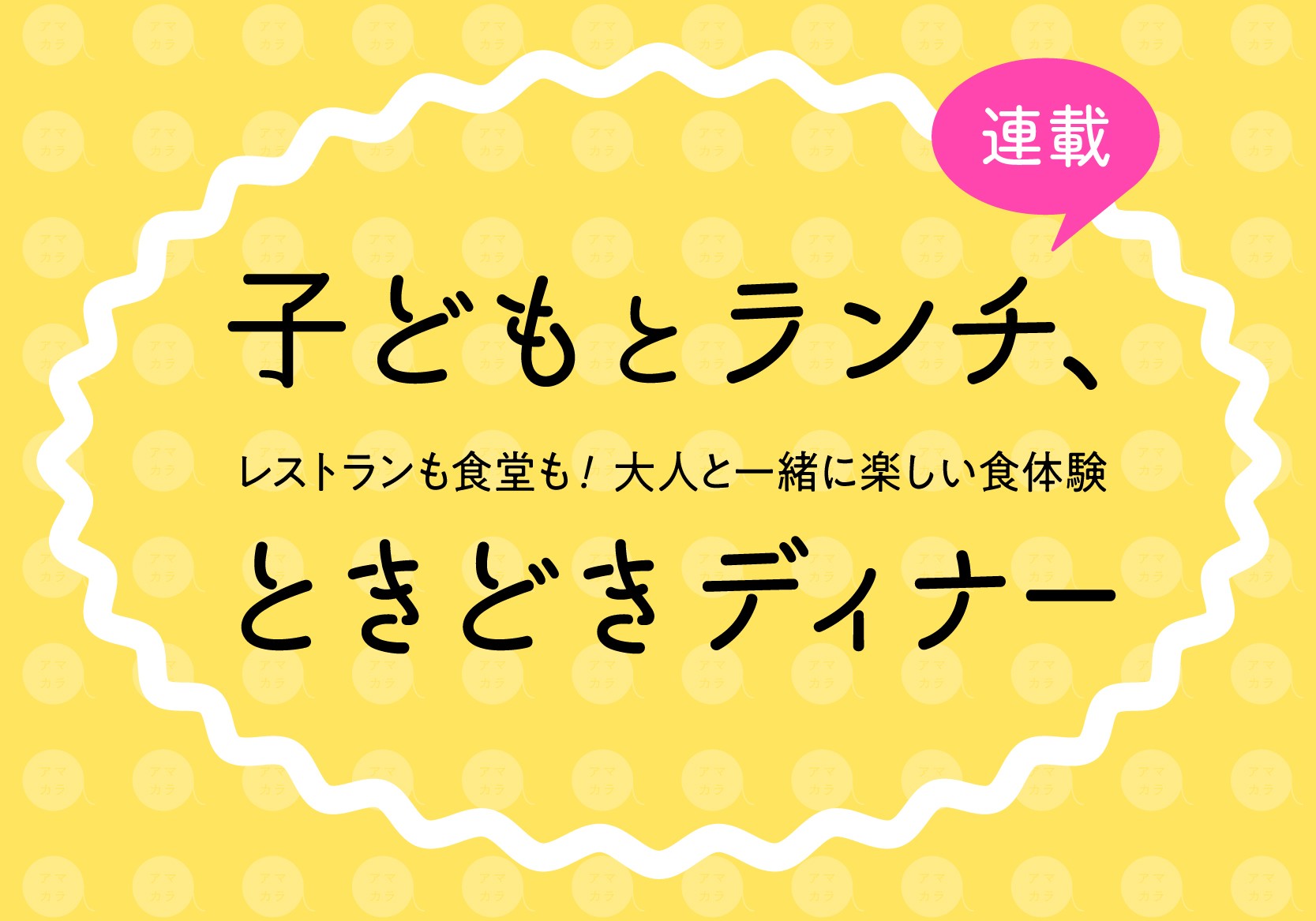十五代目の守破離──京都『瓢亭』の「小蕪、菊菜、伝助穴子の炊合せ」
カブらしさを守るために、蒸す
ほんのりと色付いたカブは、美しい輪郭を保っている。表面がまとうのは、干し貝柱のだしだ。噛みしめると、芯からは凝縮したカブの持ち味が感じられる。見た目は、美しいカブの煮物そのものだが、味わいはどこか違う。素材感が際立っているのだ。
カブは米のとぎ汁などで下茹でし、カツオ昆布だしで炊いて、調味して煮上げるのが一般的ですよね。そのまま一晩おいて、中心まで煮汁の味がしゅんでいるのが、おいしい煮物とされます。でも、はたして、カブらしさは生かされているのかな?と、ある時ふと思ったんです。茹でている間に、カブの旨みが湯に流れ出ているのではないかと。それで、カブの持ち味をしっかりと閉じ込めるために、蒸すことにしたんです。
カブは下茹でしてから煮るもの。それは、日本料理人に刷り込まれた慣習ではなかろうか。その仕事の意味を改めて問うてみる。髙橋さんは本質を突く料理人だ。カブに添えた穴子は、しっとりと蒸し煮にするのが定石だが、ん? 鼻に向けるこの香りは? 燻(いぶ)したような香ばしさがそこはかとなく感じられる。
蒸し煮にしてから、煙の香りをまとわせているんですよ。晩秋から冬になると、枯葉を集めて焚き火したり、火鉢で暖を取ったりするでしょう。燻香はこの時季の香りを想起させます。それを少しまとわせることで、炊合せに食材だけでない季節感を添えました。
日本料理のだしは、もっと多彩でいい
『瓢亭』の基本のだしは、酸味や渋みが出やすいため、カツオ節ではなくマグロ節と昆布で引くという。そこに酒・みりんを合わせた八方だしでカブの煮汁を割って、菊菜をさっと煮上げる。カブの煮汁のベースは、干し貝柱のだしだ。旨みは強いが、節のだしに比べて香りは穏やかで、カブや青菜の持ち味が率直に感じられる。
ここ数年は一番だしを引く量がぐっと減りました。どんな食材を調理するにも同じだしを使うことに疑問を持つようになって、今では様々なだしを引いています。野菜の皮や切れ端から取る野菜だしは、白味噌椀に向きますし、ベジタリアンやビーガンのニーズにも対応できます。エンドウ豆の料理にサヤから取っただしを合わせたり、トマトのだしも使います。魚のアラや鴨など、だし素材はいくらでもありますから。日本料理は、もっとだしのバリエーションがあっていいと思うんです。
髙橋さんは、今回のワンデッシュに炊合せを選んだ。旬の素材をそれぞれ最適に煮て盛り合わせる古典的な料理だ。厨房で拝見した仕事は、カブを八方にむく庖丁の技も、持ち色を損なわず、形を保つ煮方も、丁寧で、ため息が出るほど美しい。漆器に盛り合わせれば、料亭らしい端正な姿。けれど、カブ、穴子、菊菜それぞれにさり気ない進化が潜んでいる。その匙加減の妙に、『瓢亭』の美意識が宿っている。
炊合せは季節の移ろいを表現する料理ですから、旬の素材を扱う指針になるんです。今年のカブは出回るのが遅いな、でも、甘みは強くてしっとり煮上がるな、と見極める。そして、そのカブをどう炊いたらよりおいしくなるのか、どんな食材を合わせるといいか、何のだしを使うべきかと考えます。小カブの後は海老芋を使い、冬が深まると、いよいよ聖護院カブラの季節です。そうして1年を通して炊合せを作り続ける。僕が料理人である限り、ずっと向き合っていく料理なんです。
十五代目の守破離が体現するもの
『瓢亭』は南禅寺の門前の茶屋として庵を結び、天保年間から400年の歴史を重ねてきた京都きっての料亭だ。名物の瓢亭玉子や朝がゆがつとに有名だが、一棟ずつ独立した本店の茶室で昼夜に供すのは、茶懐石を基本とした京料理。老舗の懐石料理と聞くと、厳格で古めかしいイメージがあるが、『瓢亭』は進取の気質をもって、新しい味も生み出している。
十四代目の父は、旬魚の「味噌幽庵焼」を考案しました。幽庵焼は醤油をベースにした漬け地を使うのが基本ですが、そこに白味噌を合わせたワケです。今ではすっかり定着した仕事ですが、当時は新しい発想だった思います。僕は、お造りにトマト醤油を取り入れました。長く商いを続けさせていただいている料亭だからこそ、時代に合わせたプレゼンテーションも必要。『瓢亭』の味を守るために、その味が古くならないような変化を重ねているんです。
髙橋さんは代を継ぐ前から、多くの出仕事を経験してきた。海外で京料理を振る舞った経験は数知れない。ワインの造り手を招いてのメーカーズディナーなど、毎月のようにイベントもこなしている。2018年には「東京ミッドタウン日比谷」に出店。店内にカウンターを設え、新たな料亭のもてなしの形に挑んで7年が過ぎようとしている。
うちには『瓢亭』の“型”があります。茶室に高膳(たかぜん:脚の長いお膳)を配し、茶の心をもって懐石料理を供す。こうした日本の食文化を次代に繋ぐことは、うちのような料亭の使命でもあると思います。その型を確固たるものにしたのが父の代とすると、僕の時代に必要なのは守破離。インバウンドも含めて、日本料理のニーズは広がっています。新たなファンというか、『瓢亭』の“型”の理解者を増やすためにも、間口は広げておきたい。僕は様々な経験をさせてもらったので、柔軟に、無理のない変化を重ねていきたいと思っています。
“型”という伝統を守りながらも、“守破離”の精神で変化を続ける。さりげなく、質実に。「変わっていないように変える」「無理やりでなく、自然な形で」と十五代目は言う。『瓢亭』の炊合せは、そんな“変化の美学”を体現している。
data
- 店名
- 瓢亭
- 住所
- 京都府京都市左京区南禅寺草川町35
- 電話番号
- 075-771-4116
- 営業時間
- 朝がゆ8:00~11:00(10:00LO。※7/1~8/31の期間限定)、昼12:00~15:00(13:00LO)、夜17:00~21:30(19:30LO)
- 定休日
- 水曜、不定休あり
- 交通
- 京都市営地下鉄蹴上駅から徒歩7分
- 席数
- 個室5室(2~28名)
- メニュー
- 朝/朝がゆ(7/1~8/31)7590円、鶉がゆ(12/1~3/15)18975円、昼/懐石料理31625円~、夜/懐石料理37950円~。サービス料10%別。
- 外国語メニュー
- あり
- 公式サイト
- http://hyotei.co.jp/
- https://www.instagram.com/kyotohyotei/

writer

中本 由美子
nakamoto yumiko
青山学院大学を卒業し、料理と食の本を手掛ける東京の「旭屋出版」に入社。4年在籍した後、「あまから手帖」に憧れて関西へ。編集者として勤務し、フリーランスを経て、2010年から12年間、編集長を務める。21年、和食専門ウェブ・マガジン「和食の扉〜WA・TO・BI」を立ち上げ、25年に独立。フリーの食の編集者&記者に。産経新聞の夕刊にて「気さくな和食といいお酒」を連載中。
recommend